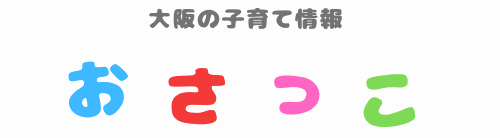家庭を支える主要な経済的支援制度
子育てには経済的な負担が伴いますが、国はいくつかの手当制度を通じて、その負担を軽減するための支援を行っています。ここでは、全国共通で利用できる主要な経済的支援制度について解説します。
A. 児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
目的と支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等に支給されます。2024年10月からは、支給対象が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長される予定です 2。原則として、児童および養育者が日本国内に居住していることが条件となります。所得の高い方の親(主たる生計維持者)が受給者となりますが、公務員の場合は勤務先から支給されるため、申請も勤務先に対して行います。
支給額(1人あたり月額)
児童手当の支給額は、児童の年齢や第何子かによって異なります。
- 現行制度(2024年9月分まで):
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前:第1子・第2子 10,000円、第3子以降 15,000円
- 中学生:一律10,000円
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯(特例給付):児童1人あたり月額5,000円
- 2024年10月分からの改正後 :
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給対象が高校生年代まで延長されます。
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上高校生年代:10,000円
- 第3子以降(年齢に関わらず高校生年代まで):30,000円に増額されます。
- 第3子のカウント対象となる子の範囲が、22歳年度末までの経済的負担のある子に拡大されます。
この2024年の大幅な改正は、子育て世帯への経済的支援を一層強化しようとする国の明確な意思の表れと言えるでしょう。所得制限の撤廃や対象年齢の拡大、特に第3子以降への手厚い給付は、少子化対策としての側面も持ち合わせています。
申請手続きと支給時期
出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合、事由発生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります 3。公務員は勤務先に申請します。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなるため、迅速な手続きが求められます。この「15日ルール」は、保護者が制度を理解し、能動的に行動することを前提としており、注意が必要です。
- 現行の支給時期:原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
- 2024年10月分からの支給時期:毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)に、それぞれの前月分までの2ヶ月分が支給されるようになり、より家計管理がしやすくなることが期待されます。
一般的な必要書類 (市区町村により異なる場合があります)
申請には、主に以下の書類が必要となります。マイナンバー制度による情報連携で一部書類が省略可能になる場合もありますが、個々の状況に応じた書類が必要となるため、事前に市区町村に確認することが賢明です。
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し(厚生年金加入者など、被用者保険に加入している場合)
- 請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- その他、児童と別居している場合の「別居監護申立書」や、市区町村を転入した場合の所得証明書など、状況に応じて必要な書類があります。
留意点
父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している親に優先的に支給されます。また、児童が児童養護施設などに入所している場合や里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給されます。
B. 育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児のために休業する際に、休業中の所得を保障し、育児休業の取得を促進することを目的とした制度です。
支給対象となる条件
以下の条件を満たす方が対象となります。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得すること(保育所に入所できないなどの特定の理由がある場合は、子が1歳6ヶ月または2歳に達するまで延長可能)。
- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上の月)が12ヶ月以上あること 7。
- 育児休業期間中の1支給単位期間(通常1ヶ月)において、就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)であること 7。
- 休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと。
給付額の計算と支給期間
給付額は、原則として休業開始前の6ヶ月間の賃金(賞与を除く)を180で割った「休業開始時賃金日額」に基づいて計算されます。
- 給付率:
- 育児休業開始から180日間:休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%
- 育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 50%
- 休業開始時賃金日額には上限額と下限額が設定されています。
- 育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税の算定基礎に含まれません。また、育児休業中に給与の支払いがない場合、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。
申請手続き
原則として、事業主が管轄のハローワークに必要な書類を提出して行います 7。従業員本人が希望すれば、自身で申請することも可能です。
- 初回申請に必要な主な書類:
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子健康手帳の写しなど、育児の事実や出産予定日、出生日を確認できる書類
- 賃金台帳や出勤簿など、賃金額や支払状況を確認できる書類
- 2回目以降は、ハローワークから交付される育児休業給付金支給申請書を用いて、原則2ヶ月ごとに申請します 10。
- 電子申請(e-Gov)も可能です。
事業主が手続きを代行することが一般的であるため、従業員はまず勤務先の人事・労務担当者に育児休業の取得と給付金申請の意向を伝え、必要な情報を提供します。事業主には、従業員に対して育休制度の説明と意向確認を行う義務があります。
2025年4月からの主な改正点
育児休業給付制度は、働きながら子育てをする人々をより強力にサポートするため、改正が予定されています。
- 出生後休業支援給付金:新たに創設される給付金で、子の出生後8週間以内に父母双方が14日以上の育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の13%相当額が最大28日間支給されます。これにより、既存の育児休業給付金(67%)と合わせて、休業開始時賃金の80%(手取りで10割相当)の給付が受けられるようになります 7。この制度は、特に父親の育児休業取得を促進し、「共働き・共育て」を後押しする狙いがあります。
- 育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育するために短時間勤務制度を利用している場合に、短時間勤務中に支払われた賃金の10%が支給される制度です 8。
これらの改正は、特に休業初期の経済的負担を軽減し、男女双方の育児参加を促すことで、より柔軟な働き方と子育ての両立を支援しようとする政策の方向性を示しています。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
子の出生後8週間以内に、4週間(28日)を上限として2回まで分割して取得できる「産後パパ育休」に対応する給付金です。給付率は休業開始時賃金の67%で、通常の育児休業給付金とは別に申請できます。
育児休業給付制度は、延長の条件や「パパ・ママ育休プラス制度」(両親ともに育休を取得する場合に休業可能期間が延長される制度)7など、個別の状況に応じた規定が細かく定められています。そのため、詳細は勤務先やハローワークに確認することが不可欠です。
C. 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に対し、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象と障害の程度
20歳未満で、法令により定められた程度(重度または中度以上)の精神または身体の障害の状態にある児童を養育している父母、または父母に代わってその児童を養育している方が対象です。
支給額(1人あたり月額・令和7年4月適用)
- 障害等級1級(重度):56,800円
- 障害等級2級(中度):37,830円
この手当は、障害のある子どもを育てる家庭が直面する特有の経済的・精神的負担を考慮したものであり、その給付額も比較的高く設定されています。
所得制限
受給資格者本人、その配偶者、または生計を同じくする扶養義務者(同居の親族など)の前年の所得が、定められた限度額以上である場合は支給されません。
支給対象外となる場合
児童が児童福祉施設などに入所している場合や、所得制限を超過した場合は支給されません。
申請手続きと支給時期
申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。
- 主な必要書類:
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本
- 児童の障害の程度に関する医師の診断書(所定の様式)
- 請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカード
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 支給時期:原則として、毎年4月、8月、12月(または11月)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
継続して受給するための手続き
手当の受給資格や所得状況を確認するため、以下の手続きが必要となる場合があります。
- 所得状況届:毎年提出が必要な場合がありますが、所得が継続して制限額を超えている場合は提出不要となることもあります。
- 障害診断書提出届(有期再認定):児童の障害の状態に応じて、定期的に医師の診断書を再提出し、障害程度の再認定を受ける必要があります。これを怠ると手当の支給が停止されるため、注意が必要です。
この制度は、所得制限や定期的な障害認定の更新など、継続的な受給には一定の条件と手続きが伴うため、受給者はこれらの要件を常に意識しておく必要があります。
D. 子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯生活支援特別給付金は、食費等の物価高騰に直面し、特に影響が大きい低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から支給されるものです。
対象者(令和5年度の例)
この給付金は、恒常的な制度ではなく、経済状況等に応じて臨時に編成されることが多いため、対象者や支給額はその都度定められます。令和5年度の例では、以下のような世帯が対象となりました。
- 児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)
- 上記以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯や、家計が急変し住民税非課税相当の収入となった世帯
給付金の性質
この給付金は、児童手当のような定期的な月次支給ではなく、一時金または特定の期間における特別な給付として支給されることが多いです。例えば、「令和5年3月予備費分」といった形で予算措置がなされることがあります。これは、経済状況の変化に迅速に対応し、特に困難を抱える層へ集中的に支援を届けるという、機動的な政策対応の現れと考えられます。
申請方法
児童扶養手当受給世帯など、既に他の制度で低所得であることが把握されている世帯へは申請不要(プッシュ型)で支給される場合がある一方、それ以外の対象世帯(例:家計急変世帯)は申請が必要となる場合があります。詳細な申請方法や条件は、給付が実施される際に自治体等から広報される情報を確認する必要があります。
このような臨時的な給付金は、その時々の経済情勢や社会状況に応じて設計されるため、常に最新の情報を自治体のウェブサイトや広報で確認することが重要です。特に、申請が必要なケースでは、情報を見逃すと受給機会を失う可能性があるため、注意が求められます。
表1:主な全国共通の経済的支援制度概要
| 制度名 | 主な対象者 | 概要・給付額の目安(月額) | 主な受給資格・注意点 | 主な申請窓口 |
| 児童手当 | 0歳~高校生年代までの児童を養育する者 | ・0~3歳未満:15,000円 ・3歳~高校生:10,000円 ・第3子以降:30,000円 (2024年10月~所得制限撤廃) | 国内居住、15日以内申請、公務員は勤務先 | 市区町村役場 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険被保険者で育児休業を取得する者 | 休業開始時賃金の67%(当初180日)、その後50%。 2025年4月~出生後休業支援給付金(13%上乗せで最大80%)新設。 | 雇用保険加入、休業前の就労実績、休業中の就業制限あり | ハローワーク(原則事業主経由) |
| 特別児童扶養手当 | 精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する者 | ・1級(重度):56,800円 ・2級(中度):37,830円 (令和7年4月~) | 所得制限あり、児童の施設入所時は対象外、定期的な障害再認定必要 | 市区町村役場 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金 | 低所得の子育て世帯(児童扶養手当受給者、住民税非課税世帯など) | 支給額は実施時により異なる(例:児童1人あたり数万円の一時金) | 臨時的な給付のため、対象・金額はその都度決定。申請が必要な場合あり。 | 市区町村役場(実施時) |